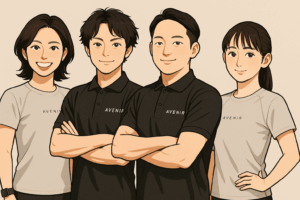社内の動向について喜ばしいことがあったので、事務局長としてコラムを出したいと思い、キーボードで指を走らせる。
まず1番に、上層部の透明化がクリアにはっきりと本格的に行われていて、喜ばしいということだ。
透明化の背景
上層部の透明化が、なぜ必要になったかを語らせてほしい。
経緯としては今までは現場と上層部で小規模な組織であったため、互いにアクセスしやすく距離も近かった。
そこは信頼関係で成り立っていたというものもあるが、その信頼を築くためのコミュニケーションが実にしっかりとここで設けられていた。
自然、それも自然とだが、組織が大きくなるにつれ、コミュニケーションの量が減るのは必然的である。
一人当たりのコミュニケーションというのは、だんだんだんだんと減っていき、必要なメンバーのみのコミュニケーションになっていく。
また新人は新人で、組織がしっかりしてきたからこそ行える特別なカリキュラム新人研修が設けられ、1ヵ月かけて行うため、全く別の動きとなっている。従来からの流れでは全くもってできなくなってきたのである。
これが、約半年も経ってないくらいの出来事である。とてつもない速さである。
そこに対しては、悲しみがあるというものではなく、組織が多くなってきたものの対価として受け止めている。
だからこそ、これまでは代表とのコミュニケーションの中で会社の本質的な考えや方針というものを受け取ることができた新人たちがそれをできなくなりつつある。
だからこそ、会社の本質的なコミュニケーションをマニュアルやルールといったような形にしなければならいと考えている。
逆を言えば、マニュアルはただの行動規範ではなく、代表や上層部の考えや方針が盛り込まれているということである。
さてここまでが現場の話だが、だからといって上層部が変わらなくてもいいのかというと、それは全くもって間違いである。
上層部は上層部で、組織が大きくなったときの形にならないといけない。
そのためには我々が行っていったことを、上層部が行ってきた形を変えなければならない。
上層部こそ、組織に合わせて敏感に察知し、変わらないといけないのである。
その中で1つの変化する点として、上層部の透明化である。
しかし、上層部の透明化は、上層部にとって、何も難しいものではない。
上層部だって本部の人間だって血の通った人間だ。
私からすると血が通いすぎている感じもする。
熱く、優しく、敏感で、自分の時間を誰よりも他人のために使う、そういったメンバーである。
先週と今週の2度にわたって透明化を行ってきたが、それに対して何か会議の内容が変わったかと言われると、私はこれは全くもって感じない。
嘘か真かと問われれば、それはあなた次第といったところだが、私はそう明言する。
現場のための組織
私にとって本部マネージャーミーティングは何者でもない、現場のためのミーティングだと考えている。
現場の声を逐一上げ、個々のスタッフに対して、アヴニールという企業とのマッチングを定める。
もちろんどんだけ知り尽くした代表であっても、その判断を独断にせず、チームに意見を委ね、アヴニールとして平準化させる。
ただただそれだけのことである。
私は幾度となく、現場の声が大きなものを動かしてきたことを見てきた。
カウンセリングシートがアナログだから、デジタルにするべきという一声でiPadを70万円以上かけて一括購入する。
体験のために店舗設備が整っていないという一言で、翌日にレンタカーを借り、店舗搬入。
やりたいワークがあるという一声で、マシンの発注量を予定より50万円分増やす。
それがアヴニールである。
本部やマネージャーや私のお給料は全て現場のトレーナーのおかげで成り立っていると、代表は言う。
だからこそ私も、何よりも現場を大切にしたい、現場を第一優先にしたいと考えている。
今までのアヴニールには、誤解があった
今のアヴニールで、まず行わなければならないのは誤解を解くことだと私は考えている。
上層部と現場の誤解というのが少なからずあるのが組織であるとは思っている。
だが、その誤解というのは極力減らす。
それが良い組織としての務めではないだろうか。
理念やビジョンに共感して入社するスタッフたちが、根底で合わないわけがない。
だからこそ、上層部は上層部だけの握り締めている情報というものを、できるだけ手放すことを今回は決意したのだと感じる。
上層部の人たちは、やってきたことの過ちを認め、そこに対し愚直に改善し、格好悪いかっこよさを持つ。
そんな素晴らしい組織だと私は思う。
前回や前々回のミーティングは実にスムーズに行われた。
むしろ現場のスタッフが、本部のマネージャーのミーティングに入ることで、より明確で強い意思のあるミーティングができたと感じられた。
そしてこの取り組みで3名の現場スタッフが時間を作ってくださり参加してくださっている。
年齢も性別もポジションも役割も目標もそれぞれ違う3人だったが、全員口を揃えて「良い会議だった」という言葉をいただいている。
会議の内容は、会社を一つでも前に、全職全身で進めるために行われている会議であり、一切の妥協はない。
現場スタッフがいようが、会議が止まってしまえば会社は廃れていく。
だからこそ作り込む必要など一切ない。
むしろ、演じることなど一切できないのである。
会議では、スタッフの言動を厳しく取り締まるような内容もあり、またそれについて目の前で対策なども考えている。
いわば現場にとって苦い、耳が痛くなるような話し合いもあった。
逆を言えば、上層部の連携不足や意味合いの違いのすれ違いなどを改めて発見し、我々が、上層部が恥ずかしいような場面もあった。
しかしそういった話し合いに参加し、三者三様の意見の中で、性格、人格の中でで出てきた言葉が「良い会議だった」という言葉ならば、まぎれもなく、私たちが行ってきた会議は、上層部の会議は、組織のための、アヴニールのための会議だったと証明されたと考えている。
これほど嬉しいことはないと私は感じた。
“働く”を教えてくれた漫画「サラリーマン金太郎」
少し話が変わるが聞いてほしい。
私が働きそのものに興味を持ったきっかけになった漫画がある。
「サラリーマン金太郎」という漫画だ。
感覚的には半沢直樹みたいな、ビジネスと働きと生き方を投げかけてくるような物語だ。
働くというのは、ただお金を稼ぐための行為ではない。
パートやアルバイトのように時間で決められて、そのうちに働くというものではない。
自分自身の働きで社会を動かし、その渦に社会の螺旋になるという事の本質的な意味を教えてくれるような漫画であった。
サラリーマン金太郎を簡単に説明すると、昭和世代の漫画で、
勉強などせず、むちゃくちゃ不良だが、間違ったことを間違ってると言って生きてきたような性格の金太郎が、ひょんなことから大手ゼネコンの社長の命を救い、会社へコネ入社する。
不良社会で名の通った金太郎だったが、平の末端社員からスタートし、1から努力を重ね、だんだんと成り上がっていくストーリーである。
その常識外れの奇抜で、しかし筋の通ったカリスマ的なアイディアで、会社の危機を救っていく姿が、坂本にとってとても感動的であった。
そのストーリーの中で、金太郎が新入社員に幹部の会議を見せるというシーンがあった。
金太郎は社長と縁があり、社長に直談判しに行く。
普通なら、まぁまぁありえない展開だと思いつつ、漫画では社長は、正面から向き合い、その参加を快諾する。
社長は小太りだが、めちゃカッコAだった。
もちろん参加した新入社員が幹部で話し合っていることなど微塵もわからないだろう。
だがその新入社員が興奮を覚え、組織として働く意思を断固として固めるシーンはとても印象的でかっこよく思えた。
漫画の話が長くなってしまったが、要は漫画であるようなシーンを私は今目の当たりにしているということである。
なんてかっこいいんだろう。
そういった感動を私は今まさに覚えている。
現場が輝く組織こそ、“アヴニール”
長くなってしまったが、私が言いたい事ことがある。
それは、
「アヴニールを作っているのは上層部の人ではない。
アヴニールを作っているのは現場で活躍する、あなた だ。」
上層部が動いているのは、そのアシストでしかなく、あなたの存在が1番大きく1番重要なのだ。
半沢直樹の言葉を借りるなら「感謝と恩返し」。
半沢直樹の父が半沢直樹に伝えた言葉を、私はアヴニールに使っている。
アヴニールのために居てくれてありがとう。
あなたが何を思っていようと、あなたの1分1秒はアヴニールのために行われていることであり、それは紛れもない事実である。
ミスを恥じる必要はない。トラブルを恐れる必要はない。
アヴニールは、あなたを決して欺いたり批判したりはしない。
共に頑張れることに、喜びを感じています。